1つ前のエントリー「銀河戦:小倉久史七段が三間飛車を駆使し決勝トーナメント進出」にて、小倉七段の多彩な構想を「虹色三間」と評したあと、「では実際、虹色三間の7つのバリエーションとは何だろうか?」という疑問が沸いてきた。
「虹色四間」
ここで、元ネタとなっている「虹色四間」についてそもそもご存じない方のために説明しておこう。
「虹色四間」は、約10年前に「週刊将棋」誌上で連載されていた、つのだじろう著の将棋漫画である。私自身「週刊将棋」はほとんど読んでいなかったし、今や内容をほとんど覚えていないが、『7つのバリエーションの四間飛車を「虹色四間」と総称し、これらを駆使して主人公がライバルとの戦いに挑む』、といった内容だったと思う。たしか、
- 立石流
- 対居飛穴の向かい飛車振り直し
などがあったと思うが、7つすべてを思い出すことはできない。下記のWikipediaにも載っていない。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
「5五の竜」
本作は、もっとずっと前に連載していた、同著者による「5五の竜」の続編に近い内容といえる。私は「5五の竜」はすべて読んだはずなのだが、こちらも内容をほとんど覚えていない。
「5五の竜」と「虹色四間」の概要については、下記Wikipediaを参照あれ。
『5五の龍』(ごごのりゅう)は、つのだじろうによる将棋をテーマとした漫画作品。当稿では本作の続編ともいえる『虹色四間』(にじいろしけん)についても解説する。
| 5五の竜 (1) (中公文庫―コミック版) | |
| つのだ じろう
中央公論社 1995-11 |
|
ただ、「5五の竜」における「飛騨白川郷の大家族の家!合掌造りの駒組み!」という見事な布陣は、名フレーズとともに今でも脳裏に焼きついている。ネットで調べてみたら、「ギズモのつれづれ将棋ブログ」様の「将棋漫画「5五の龍」より」というエントリーで、この対局の模様が紹介されていた。
三間飛車における7つのバリエーションとは
さて、いよいよ本題。検討してみたところ、都合よくぴったり7つとなった。
- コーヤン流(対居飛穴の▲5七銀型美濃囲いの布陣をひっくるめて。したがって「真部流」も含む)
- 対居飛穴・相穴熊
- 対居飛穴・向かい飛車への振り直し
- 対居飛穴・玉頭銀(「下町流三間飛車」(小倉久史七段 著)
で解説されている構想*1。)
- 石田流(▲9七角と上がる古典的石田流や、角道を止めて6八や5九に角を引く石田流をひっくるめて。楠本式石田流もこれに含める)
- 升田式石田流(角道を止めない、角交換辞さずの石田流をひっくるめて。したがって「新・石田流(7手目▲7四歩)」も含む。立石式石田流もこれに入れてしまうとする)
- 2手目△3二飛戦法(詳しくは「2手目の革新 3二飛戦法」(長岡裕也四段 著)参照
いかがだろうか。これを毎局毎局使い分け、しかも勝ち続けることができたら、究極の三間飛車党といえるだろう。

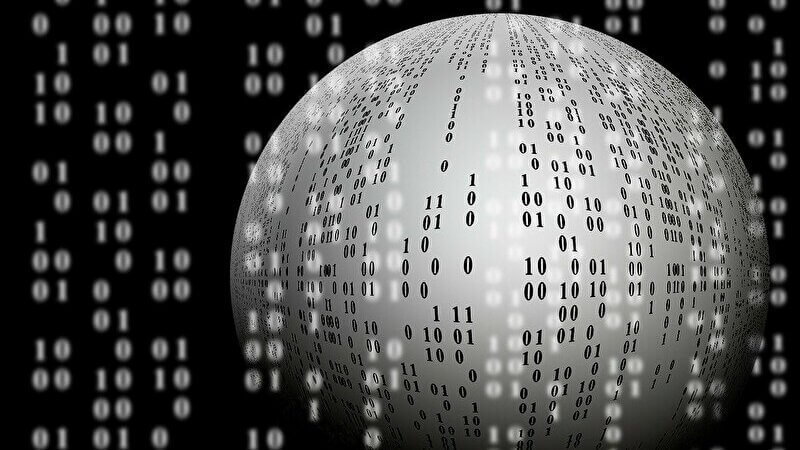
コメント